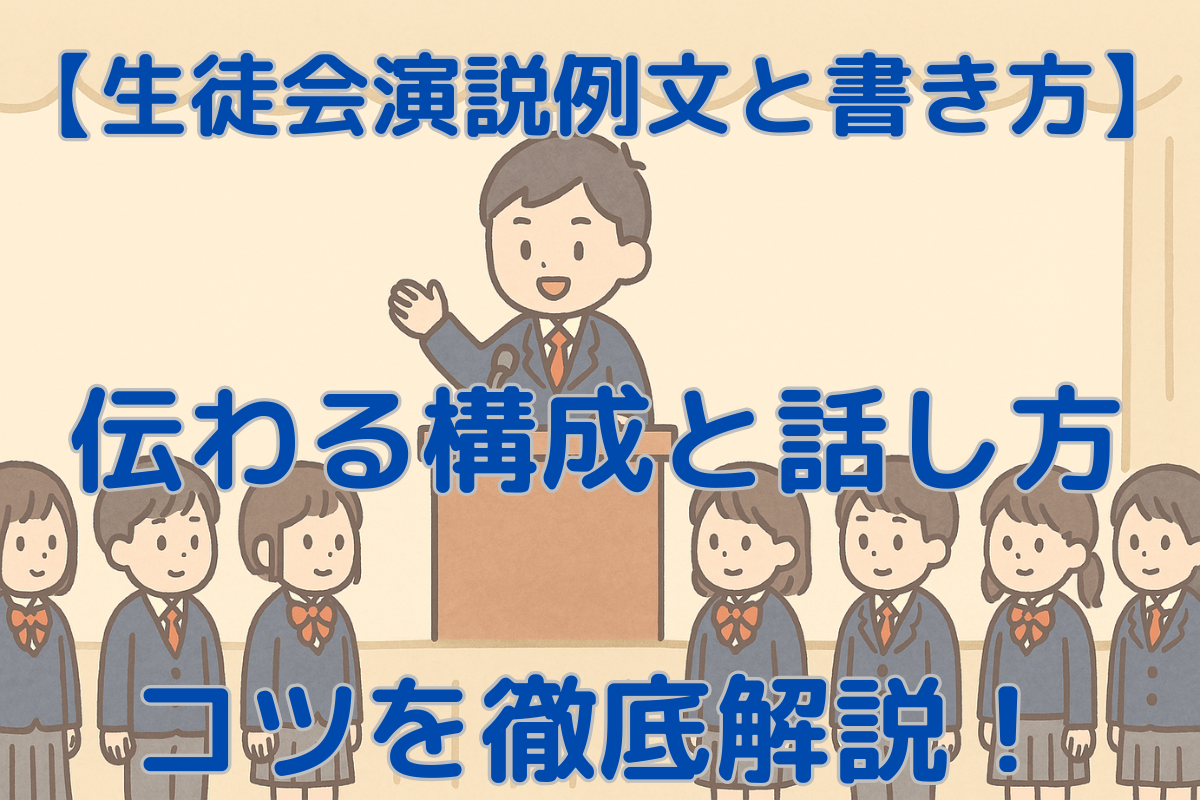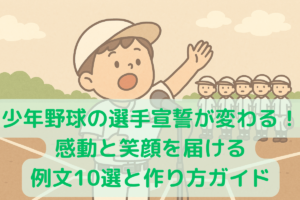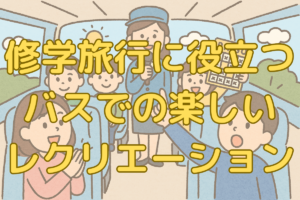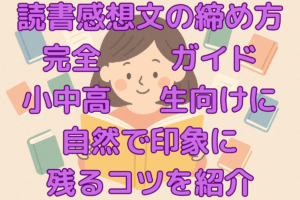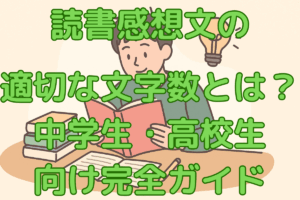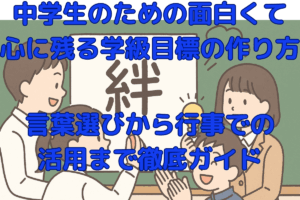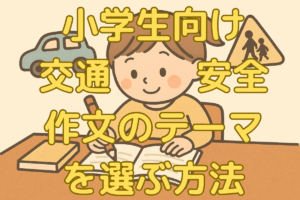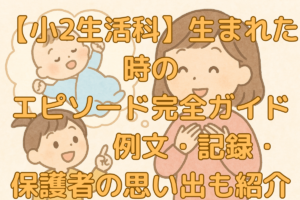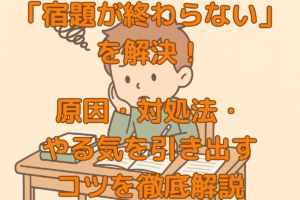「生徒会演説って、何をどう話せばいいの?」
そんな悩みを抱えているあなたへ。この記事では、はじめて生徒会に立候補する人でも安心して準備ができるよう、演説のコツや構成、実際に使える例文までをわかりやすく紹介しています。
伝えたい想いはあるけれど、どう伝えればいいのかわからない。そんな時こそ、正しいステップと少しのコツが力になります。あなたの言葉で、あなたらしい演説をつくるために――このガイドがきっと役に立ちます。
生徒会演説の重要性
生徒会とは?その役割と目的
生徒会とは、生徒自身が学校生活をよりよいものにするために活動する組織です。学校行事の運営や校則の見直し、学校環境の改善など、学校全体に関わる幅広い活動を行います。生徒会の目的は、生徒の意見を集めて形にし、学校生活をより充実させることにあります。また、協調性や責任感、リーダーシップを育む場としても大きな意義があります。
生徒会演説がもたらす影響
生徒会役員になるためには立候補し、演説を通じて自分の考えやビジョンを伝える必要があります。この演説は、単なる立候補表明にとどまらず、聴衆である同級生や後輩に大きな影響を与えるチャンスでもあります。演説の内容や話し方ひとつで、共感や信頼を得られるかどうかが決まり、選挙結果にも直結します。
成功につながる生徒会演説の意義
成功する生徒会演説は、自分の想いをしっかりと伝えるだけでなく、聴いている人の心を動かします。「この人になら任せられる」と思わせる演説は、選ばれるための大きな一歩です。また、演説の準備を通して、自分の考えを整理し、言葉で表現する力も磨かれます。演説は単なる行事ではなく、自分自身を成長させる絶好の機会でもあるのです。
効果的な演説のためのコツ
聴衆を意識したスピーチ
演説は一方的に話すものではなく、聴いてくれる人たちとの心のやり取りです。まず意識したいのは、「誰に向けて話すのか」。小学生・中学生・高校生では関心事が異なりますし、学年によっても伝えたい内容や言葉選びが変わってきます。例えば、1年生にはわかりやすく丁寧な表現を、同学年や上級生には対等な目線の語りかけが効果的です。
また、演説を聴く側は「この人は本気なのか?」「自分たちにどんなメリットがあるのか?」を見極めようとしています。ですので、「私は〇〇を実現したいです」という理想だけでなく、「皆さんの声を大切にしたい」「〇〇に困っている人のために動きたい」といった共感を生む言葉が非常に重要です。
自己紹介で印象を強める
演説の冒頭で行う自己紹介は、ただ名前を名乗るだけの場ではありません。聴衆が「この人、話を聞いてみようかな」と思うきっかけをつくる大事なポイントです。
たとえば、「〇年〇組の〇〇〇〇です。クラスでは『冷静で責任感がある』と言われることが多いです」といったように、自分の人柄や特徴をさりげなくアピールすることで、印象が強く残ります。
さらに、自己紹介の中でちょっとしたエピソードやユーモアを交えるのも効果的です。たとえば、「実は朝がとても苦手で、目覚ましを5個使っています」など、親しみやすさが加わると、聴衆との距離が一気に縮まります。
具体的なビジョンを提示する方法
ただ「みんなが楽しめる学校にしたい」と言っても、それだけでは説得力に欠けてしまいます。重要なのは、「どうすればそうなるのか」という具体的な行動を示すことです。
たとえば、「学校生活をもっと楽しくしたい」というビジョンがある場合は、「昼休みに音楽を流す」「学年ごとの交流イベントを企画する」など、明確な提案を加えることで、聴く人は「この人なら実行してくれそう」と期待を抱きやすくなります。
また、その提案が実現可能であることも伝えると、より信頼が高まります。「〇〇委員会と協力すれば実施できると思います」といったように、裏付けとなる考えも加えておきましょう。
生徒会演説の構成
演説の基本的な流れ
説得力のある演説には、しっかりとした構成があります。基本的な流れは以下の通りです:
自己紹介と立候補の理由
まずは自分の名前と学年・クラスをはっきりと伝え、その後に「なぜ立候補したのか」を簡潔に述べます。ここでのポイントは、自分の熱意を素直に表すこと。「〇〇がもっと良くなってほしい」「この学校が好きだから何か役に立ちたい」など、個人的な思いや動機は、聴く人の共感を得やすくなります。
学校や生徒の現状について触れる
「今、〇〇に困っている人がいる」「〇〇の活動がもっと注目されるべきだと思う」など、現状への気づきを示すことで、「この人は周囲をよく見ている」と好印象を与えます。
具体的な公約や提案
問題意識を提示したあとは、それをどう改善したいのか、自分の考えや提案を伝えます。理想だけでなく、現実的な方法・手段をセットで伝えると説得力が増します。
協力のお願いと締めの言葉
最後は、「皆さんの協力が必要です」「一緒によりよい学校をつくっていきましょう」など、共に歩む姿勢を見せて締めくくります。簡潔で前向きなメッセージで終えると、印象が残りやすくなります。
つかみの部分の重要性
演説の冒頭は「聴くかどうか」が決まる分かれ目です。最初の数十秒で相手の興味を引きつける「つかみ」を入れることで、演説全体への関心を高められます。
つかみには以下のような方法があります:
質問形式:「皆さんは、毎日の掃除時間に不満を感じたことはありませんか?」
共感を誘う一言:「私も最初は、生徒会なんて自分に関係ないと思っていました」
短いエピソード:「去年の文化祭、準備期間にこんなことがありました…」
自分らしさを活かして、自然な導入を心がけましょう。
公約をしっかり強調する
演説の中核となるのが「公約」です。つまり、「自分が役員になったら何をするか」を伝える部分です。このとき大切なのは、「実現可能性」と「具体性」です。
抽象的な表現だけでは印象に残りづらく、信頼感も薄くなります。たとえば、「楽しい学校にします」よりも、「昼休みに音楽を流す活動を提案します」など、具体的な行動が伝わる表現を選びましょう。
さらに、公約が1つだけではなく、2〜3個用意できれば、幅広い層にアピールできます。ただし数が多すぎると印象がぼやけるので、最も伝えたいものを軸に据えて展開しましょう。
中学生におすすめの生徒会演説例文
シンプルな3分スピーチ例
時間に限りがある中で、しっかり想いを伝えるには「簡潔でわかりやすい表現」が鍵です。以下は、伝えたい内容を無理なく3分に収めた、シンプルな演説の例です。
📌 例文:
「こんにちは。〇年〇組の〇〇〇〇です。私は、もっと笑顔があふれる学校にしたいと思い、生徒会に立候補しました。
私が大切にしているのは、皆さんの『声』です。毎日の学校生活の中で、『ここを変えたい』『もっとこうだったらいいのに』と思うことはありませんか?私はその声を受け止め、行動に移す役目を果たしたいと考えています。
具体的には、委員会と連携しながら、より楽しい行事の実現や、学校生活の改善に取り組んでいきたいです。
皆さんと一緒に、よりよい学校をつくっていけるよう全力を尽くします。どうか、応援よろしくお願いします。」
🎯 ポイント:
立候補の理由 → 公約(学校を良くしたい)→ 具体的な姿勢(「声」を聴く)というシンプルな構成。
難しい言葉を使わず、誰でも理解しやすい文章にまとめるのがコツです。
ユーモアを交えた演説例
個性を出したい、印象に残るスピーチにしたいという場合は、少しユーモアを交えるのも効果的です。ただし、ふざけすぎず、まじめな思いとのバランスが大切です。
📌 例文:
「こんにちは。〇年〇組の〇〇〇〇です。よく『真面目そうだね』と言われますが、実は朝がとても苦手で、目覚まし時計を3つ使ってやっと起きています。
そんな私ですが、ひとつだけ誰にも負けない自信があります。それは、コツコツと物事を続ける力です。
私は、生徒の皆さんがもっと気持ちよく学校生活を送れるように、毎週『改善提案BOX』を設け、生徒の意見を集める仕組みをつくりたいと考えています。
堅苦しいイメージのある生徒会を、少しでも身近に感じてもらえるよう、皆さんの声を聴きながら、学校を楽しく、あたたかい場所に変えていきます。
どうか、あなたの一票を、私に託してください!」
🎯 ポイント:
冒頭の軽い自己紹介で親しみを感じさせ、聴衆の関心を引く。
明るさと真剣さのバランスを意識し、信頼を得られる演説に。
長文を効果的に使う方法
長めの演説になる場合は、話の構成と抑揚を工夫することが大切です。一方的に話すのではなく、「間」を意識して話すと、聴き手も疲れず、印象に残りやすくなります。
長文で効果的に伝えるには、以下の3点を押さえましょう:
話に「流れ」をつける(例:過去→現在→未来の順で話す)
要所で感情や情熱を込める
難しい言葉は避け、身近な言葉を選ぶ
📌 構成例:
学校生活での気づき(例:「去年の文化祭で気づいた課題」)
なぜ立候補しようと思ったのか(自分の想いや経験)
どんな学校を目指したいか(理想と現実の橋渡し)
みんなと一緒につくる未来(協力を呼びかける)
このように、話す時間の長さに応じて、構成や表現方法を工夫することで、伝わる力が大きく変わります。
高校生から学ぶ生徒会演説の成功例
副会長の成功談
高校では、より高度な表現や責任感が求められることから、演説にも説得力と構成力が必要です。中でも、副会長として当選した先輩の演説は、落ち着いた語り口と実行力のある提案で高く評価されました。
📌 成功例の特徴:
自分の強みを冷静にアピール:「私は決して目立つタイプではありませんが、人の意見をよく聞き、調整役として動くことが得意です。」
提案に現実味がある:「SNSアンケートで意見を集める仕組みをつくります。誰もが気軽に声を届けられるようにします。」
言い切る力:「私は、役職にふさわしい責任感と行動力をもって取り組みます。」
🎯 中学生へのヒント: 高校生のように落ち着いた言葉づかいや「責任感」を強調する表現は、成熟した印象を与えます。自分の得意なことを分析し、それをどう活かせるかを伝えるのがカギです。
活動報告を含めた演説
すでに何かの活動に参加している場合、その経験を活かした演説は強い説得力を持ちます。たとえば、委員会活動や部活での工夫・挑戦を伝えることで、「実績のある人」として見てもらいやすくなります。
📌 例:
「私は図書委員として、週に一度、読書カードの更新や図書室の整理を担当しています。その中で、『もっと本に触れる機会を増やせたら』という思いが強くなりました。
そこで、生徒会に立候補し、昼休みに週1回『読書ミニコーナー』を開設したいと考えました。実現すれば、読書が苦手な人も、気軽に本に触れられる環境になるはずです。」
🎯 中学生へのヒント: まだ大きな経験がないと感じていても、小さな活動を丁寧に伝えるだけで立派な材料になります。身近なことからスタートしている姿勢は、真面目さと行動力をアピールするチャンスです。
投票を意識した訴え方
選挙演説である以上、「投票してもらうこと」が最終目的です。ただし、あからさまなアピールは逆効果になることもあるため、自然に「この人に投票したい」と思わせる工夫が必要です。
📌 効果的な訴え方:
未来を一緒に描く言葉:「皆さんと一緒に変えていきたい」
協力を促す一言:「一人の力では難しいことも、みんなの声が集まれば実現できます」
前向きな締めくくり:「どうか、私にその第一歩を踏み出す勇気をください」
🎯 中学生へのヒント: 投票は「信頼」の証です。数字や制度の話よりも、感情に寄り添った語りが、心に届く演説になります。演説の最後には、自信と謙虚さが伝わる言葉を選ぶと、より印象深くなります。
演説で意識すべき言葉の選び方
共感を呼ぶ言葉の使い方
演説で最も重要なのは、聴いてくれる人たちの「共感」を得ることです。たとえ立派なアイデアがあっても、聴く人の心に響かなければ意味がありません。だからこそ、言葉の使い方には細心の注意を払いましょう。
共感を呼ぶには、「自分のことばかりを話さない」ことが大切です。たとえば、「私は〇〇を実現したいです」と言うよりも、「私たちみんなで〇〇を実現したいと思っています」といったように、“私”ではなく“みんな”という主語にすることで、一体感が生まれます。
また、相手の気持ちに寄り添う言葉――「困っている人がいると聞きました」「私も同じように感じたことがあります」などを入れると、共感がぐっと深まります。
強調すべきキーワード
演説中に特に意識して使いたいのが「印象に残るキーワード」です。何度も耳にする言葉や、心に刺さる言葉は、演説後の記憶に強く残ります。以下のようなキーワードは、繰り返し使うと効果的です。
「一緒に」「みんなで」:協力・連帯感を演出できる
「行動します」「実行します」:頼りがいを示す
「声を届けます」「意見を大切にします」:親近感や信頼感につながる
「変えていきたい」「つくりたい」:未来に向かう力を感じさせる
こうしたキーワードは、演説のはじめ・中盤・終わりにそれぞれちりばめることで、印象に残りやすくなります。
聴衆に響く言葉の具体例
実際に使いやすく、効果的な言い回しをいくつか紹介します。状況に応じてアレンジし、自分の言葉として使ってみてください。
目的 言い回しの例
共感を得る 「同じように感じている人もいると思います」
「私もその一人です」
自分の姿勢を伝える 「私は行動で示します」
「有言実行を大切にします」
仲間意識を高める 「この学校を、もっとみんなが笑顔になれる場所にしたい」
「一緒に変えていきましょう」
印象を残す 「あなたの一票が、未来を動かします」
「今日この瞬間から、私の挑戦が始まります」
🎯 言葉選びのコツまとめ:
難しい言葉より、やさしくて身近な言葉を選ぶ
自分だけでなく「みんな」を意識した語り方を
同じ言葉を繰り返すことで、印象を深める
感情や熱意を、素直に言葉にする勇気を持つ
言葉には、人の心を動かす力があります。だからこそ、自分の思いを正直に、丁寧に届けるために、言葉選びには時間をかけてみましょう。
提案する行動計画
具体的な提案を考える
演説で公約を伝える際に重要なのは、「理想を語るだけで終わらせない」ことです。「こんな学校になればいいな」と願うだけでは、聴衆の心は動きません。「では、そのために何をするのか」を明確にすることで、実現への本気度が伝わります。
例えば、
「休み時間に外で遊ぶ生徒が増えるように、校庭に簡易ベンチを設置したい」
「意見箱を毎月開いて、生徒の声を集めたい」
「掃除を分担するシステムを見直して、負担を平等にしたい」
といったように、具体的な形で提案を示すことが大切です。
実現可能な計画の立て方
提案は、大きければいいというものではありません。「実現できそうかどうか」が大きなカギになります。だからこそ、「それって本当にできるの?」と聴衆に思わせないための工夫が必要です。
実現可能性を高めるポイントは以下の通りです:
関係する先生や委員会の協力を前提に考える:「〇〇委員会と連携して進めます」と伝えると信頼感が増します。
段階的な実施を提案する:「まずは1学年のみで試してみて、効果を見ながら広げたい」といった段取りを示すと現実味が出ます。
予算や時間の負担が少ない提案を意識する:実現に大きな費用や手間がかかる場合、ハードルが上がってしまいます。
活動内容の提示方法
どんなに良いアイデアでも、「なんとなくいいこと言ってるな」で終わってしまってはもったいないです。聴く人に「その姿が目に浮かぶ」ように、活動の中身を具体的に伝えましょう。
たとえば、ただ「学校を明るくしたい」と言うよりも、
「毎週月曜日の朝、全校放送で『一言メッセージ』を紹介して、前向きなスタートが切れるようにします」
など、目に見える行動の形で伝えることがポイントです。
また、提案が自分の得意なことや興味のあることに基づいていれば、説得力がさらに増します。音楽が好きな人なら「音楽を使った取り組み」、絵が得意な人なら「ポスターでの情報発信」など、自分らしさを活かす工夫もおすすめです。
🎯 提案のまとめ方チェックリスト:
誰のための提案か、はっきり伝えているか
実現する方法が具体的に説明されているか
無理のない規模で、現実味のある内容になっているか
自分の経験や得意分野とつながっているか
提案は、単なるアイデアではなく「自分が責任を持って取り組む宣言」です。だからこそ、しっかり準備して、聴く人が「なるほど、それならできそう!」と思えるような内容にしましょう。
演説練習のテクニック
時間管理の必要性
演説には時間制限があることが多く、伝えたいことを全て詰め込もうとすると、かえって話がわかりにくくなったり、最後まで話しきれなかったりすることがあります。そこで重要なのが、「時間を意識した練習」です。
まずは、演説原稿を声に出して読みながら、ストップウォッチで計ってみましょう。もし想定より長い場合は、「一番伝えたい部分」を中心に、優先順位をつけて削ることが大切です。
また、話すスピードも大切です。焦って早口になってしまうと、聴いている人に伝わりづらくなります。少しゆっくりめを意識し、言葉の区切りごとに「間」を取ると、落ち着いた印象を与えられます。
緊張を和らげる方法
人前で話すことに緊張はつきものです。けれど、その緊張は「真剣に取り組んでいる証拠」。うまく付き合えば、演説の力に変えることができます。
おすすめの緊張対策は以下のとおりです:
深呼吸をゆっくり3回:気持ちを落ち着け、体もリラックスできます。
練習を繰り返す:人前での練習を重ねることで、本番への自信がつきます。
笑顔を意識する:表情がやわらぐと、聴衆との距離が縮まり、自分の緊張もほぐれます。
特に、本番前に友達や家族に聴いてもらうことで、自分では気づけなかったクセや改善点を発見できます。
フィードバックを活かす
練習の際には、ただ回数をこなすだけでなく、「他人からの意見」をもらうことが重要です。先生、友人、家族など、さまざまな立場の人から感想をもらいましょう。
フィードバックの中でも、特に注目すべき点は:
聞き取りやすさ(声の大きさ、話すスピード)
内容のわかりやすさ(話の構成、言葉の選び方)
印象に残る部分があったか(キーワードやエピソード)
指摘されたことをすぐに改善しようとする姿勢が、演説の完成度をぐんと高めます。
聴衆とのコミュニケーション
アイコンタクトの重要性
演説の最中に原稿だけを見続けてしまうと、どうしても一方的な印象になってしまいます。そこで大切なのが「アイコンタクト」です。
聴いている人の方を見ながら話すことで、「自分に向かって話してくれている」と感じてもらえるようになります。すべての人を見渡すのは難しくても、会場の左右・中央を順に見るようにすると、自然な印象になります。
アイコンタクトは、自信の表れでもあります。たとえ緊張していても、意識して視線をあげることで、堂々とした印象を与えることができます。
質問を交えた演説の作り方
演説の途中で「皆さんはどう思いますか?」など、問いかけを入れることで、聴衆を引き込むことができます。質問は、ただ投げかけるだけでなく、自分の経験や考えとセットにすると効果的です。
例:
「皆さんは、休み時間が短いと感じたことはありませんか?私は、毎日そう感じています。」
このような問いかけを入れると、「あ、自分もそう思ってる」と共感が生まれ、演説が“自分ごと”として受け止められやすくなります。
聴衆の反応を読む技術
演説中に、うなずいてくれる人、真剣に聞いてくれている人が目に入ると、自分の話が届いている実感が湧いてきます。そうした反応を意識することで、テンポや語り口を微調整することができます。
もし反応が薄いと感じたときも、焦らず、声のトーンやスピードを変えてみると効果的です。また、演説の途中で短く「ありがとうございます」と言葉を添えることで、聴衆との距離を縮めることもできます。
🎯 コミュニケーションを意識した演説にするために:
聴いてくれる人の顔を見る(視線を分散させる)
自分だけが話すのではなく、問いかけを交える
聴衆の反応を観察しながら話す余裕を持つ
まとめ:伝える力が未来を変える
生徒会演説は、ただのスピーチではありません。自分の想いや考えを、言葉で人に届けるという貴重な経験です。そこには、「自分の声で学校を動かしたい」「みんなのために何かしたい」という純粋な気持ちが込められています。
この記事では、生徒会演説の重要性から、効果的な話し方、提案の仕方、そして実際の例文までを丁寧に紹介してきました。どんなに小さな思いでも、言葉にすれば力になります。そしてその力は、聴く人の心を動かし、学校を少しずつ変えていくきっかけになります。
最初は緊張しても大丈夫です。演説は完璧である必要はなく、むしろ「この人は本気で話している」と思ってもらえることの方が大切です。あなたの言葉で、あなたらしい演説をつくっていってください。
準備を重ね、練習を重ねたその先には、きっと今までにない自分との出会いが待っています。あなたのチャレンジを、心から応援しています。